
法改正情報の一覧
社労士が取り扱う労働分野や社会保険に関する諸法令は、改正頻度が非常に高く、何かしらの改正が毎年行われています。そのため、就業規則などの社内規定を見直したり、社内制度の改定を実施するなど、法改正への対応が必要となります。
このページは、人事・労務に関する法改正のスケジュールを企業の担当者の皆さまにお届けするものです。タグを利用して、カテゴリ別に絞り込むことも可能ですので、ぜひ、情報のキャッチアップにお役立てください。
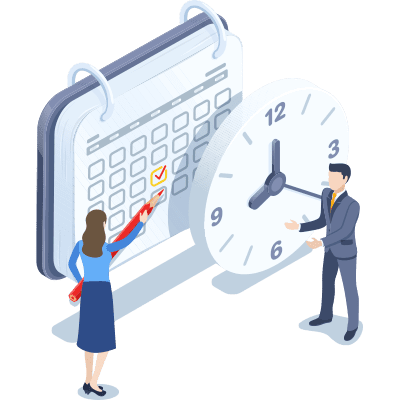
「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート
少子化対策の財源を全世代で支える仕組みとして、2026年4月分の保険料(5月納付分)より「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートします。健康保険料に上乗せされる形で労使折半により負担することになるため、給与計算システムの改修や人件費への影響の把握などを進めましょう。また、制度趣旨や控除内容を従業員へ事前に周知し、給与明細への表示や社内運用の整備を行うことも重要です。
協会けんぽが電子申請サービスを開始
2026年1月より、協会けんぽが「電子申請サービス」を開始しました。傷病手当金や出産手当金、任意継続被保険者の資格取得申出などの各種手続きをオンラインで行うことができ、郵送や窓口対応が不要となります。申請は被保険者本人や被扶養者、社会保険労務士が行う仕組みのため、スムーズに対応できるよう、マイナンバーカードの準備や申請フローなどについて、従業員へ周知することが重要です。
健康保険証の有効期限が2025年12月1日で満了
従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日をもって満了となります。今後、医療機関や薬局などを利用する際は、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を、マイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書」を提示することになります。従業員に対し、マイナ保険証の登録状況や資格確認書の取得状況を確認することが求められます。
スキルアップ目的の休暇に対する助成金が新設
従業員が離職することなく安心して教育訓練に専念できるよう、「教育訓練休暇給付金」が創設されました。自発的なスキルアップや能力開発のため、就業規則などで定められた制度にもとづき、無給の教育訓練休暇を30日以上、取得した従業員に対し、失業給付に相当する水準の給付金が支給されます。事業主には、教育訓練休暇制度の整備や、休暇取得の申請を受けた際のスムーズな手続きなどへの協力が求められます。
【2025年】最低賃金の引き上げ
10月から全都道府県で最低賃金が引き上げられます。都道府県ごとに63円から82円の引き上げとなり、全国の加重平均額は1,121円(時給)。引き上げ額の平均は66円で、1978年に最低賃金の目安制度が始まってから最高の引き上げ額です。最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、差額分を支払うだけでなく、罰金の対象となったり、企業名が公表されたりする可能性があります。
育児期の従業員が柔軟な働き方を実現するための措置が義務化
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対し、「始業時刻などの変更」「テレワークなど(月10日以上・時間単位で取得可)」「保育施設の設置運営など」「養育両立支援休暇の付与(年10日以上・時間単位で取得可)」「短時間勤務制度」の措置から2つ以上を選択し、講じなければなりません。措置の選択時は、過半数組合などから意見聴取する必要があり、従業員は講じられた措置から1つを選んで利用できます。
「年収の壁」対策に関する新コースがキャリアアップ助成金に新設
年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れて手取りが減少する、いわゆる「130万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました。労働時間の延長や賃金の引上げといった収入増加に関する取り組みを進め、パート従業員などを社会保険に加入させた事業主に対し、最大75万円が支給されます。
企業の熱中症対策が罰則付きで義務化
一定以上の温度・時間で作業する職場の事業者に、熱中症対策が義務付けられます。熱中症患者が出た際の報告体制や、症状悪化を防止する措置の実施手順などを整備し、関係者に周知しなければなりません。対策を怠ったり、義務に違反した場合はペナルティの対象となります。都道府県労働局長または労働基準監督署長から作業の停止などを命じられるほか、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【2025年度】雇用保険料率(24年度から引き下げ)
2025年度の雇用保険料率が発表されました。失業等給付などの保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに前年度の6/1,000から5.5/1,000に引き下げられます(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は7/1,000から6.5/1,000に引き下げ)。雇用保険二事業における事業主の保険料率は、前年度に引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)です。
職業紹介事業者に紹介手数料の実績公開が義務化
転職エージェントなどの職業紹介事業者に対し、紹介手数料の実績公開が義務付けられます。4か月以上の有期または無期で雇用される「常用就職」の実績が多い上位5職種について、2024年度に徴収した紹介手数料の実績(常用就職1件当たりの平均手数料率)を厚生労働省の「人材サービス総合サイト」に掲載します。また、求職者に対する違約金の規約を設けている場合、分かりやすく明示することも義務化されます。
